ADHD
CPT検査について
CPT ( 持続処理課題: Continuous Performance Test )
ADHDは、不注意・多動性・衝動性の3つの症状から診断されます。しかし、これらの症状を客観的に定量化することは難しいためこの病気の臨床診断を困難なものしています。
CPT ( 持続処理課題: Continuous Performance Test ) はADHDの中核症状のうち不注意と衝動性を客観的に評価することができうる検査方法で、Rosvold らによって開発され、現在いくつかの検査方法が臨床応用されています。
いずれの検査方法も画面上に標的刺激が提示されるとキーをクリックする単純な作業を一定時間行うものです。その反応時間や誤反応、無反応を測定することで定量化を行います。
一般的に反応時間の平均値は情報処理と動作速度、反応時間のばらつきは注意の変動性、無反応率は不注意、誤反応率は衝動性を測定しているものと考えられています。
ADHITについて
ADHITは従来のCPTを改変し、聴覚と視覚のノイズを標的刺激と同時に提示することで、不注意や衝動性の性質をより詳細に調べるとともにその検出感度を高めることを目的に開発されたCPT検査ソフトウェアです。小児神経科医である 宇野先生を中心に開発されました。
当サイトからダウンロードして無料で利用できます。
ADHIT 検査仕様書
検査の構成
検査は、説明・練習・本テストの三つのセクションによって構成される。
説明セクションでは、音声のナビゲーションとテストのデモンストレーションにより、被検者にテストの説明を行う。
練習セクションでは、本テストと同じ条件で30課題の小テストを行う。この結果はコンピュータによって自動的に評価され、被検者が検査の意味を十分理解したと判断されるまで反復される。 本テストセクションでは、総計500の課題が出題され、その結果が記録される。
検査は説明セクション、練習セクション、本テストの順に行わる。一人の検査を行うのに必要な時間はおよそ18分である。
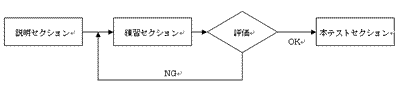
課題タイプについて
課題は、要求される反応から、ターゲット( スクリーン中央に○が表示される )と非ターゲット( スクリーン中央に×が表示される )の二つに分類することができる。被検者は、ターゲットのときはマウスをクリックし、非ターゲットのときはなにもしないことを求められる。
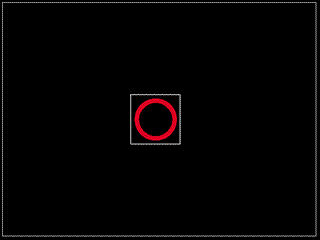
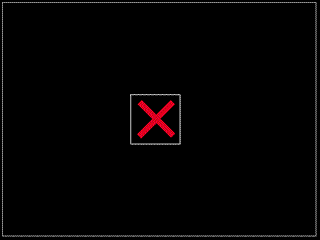
また、課題をノイズの種類から、ノイズなし、聴覚ノイズ、視覚ノイズの三つに分類することもできる。ノイズとは、被検者の行動を混乱させる目的で呈示される視覚刺激と聴覚刺激のことである。 この検査の課題には、上の組み合わせから得られる6タイプの課題( ターゲット−ノイズなし、ターゲット−聴覚ノイズ、ターゲット−視覚ノイズ、非ターゲット−ノイズなし、非ターゲット−聴覚ノイズ、非ターゲット−視覚ノイズ)が存在する。
本テストセクションのタイプ別課題数は次表のようになっている。これらが乱数によって無作為に並べ替えられた後に出題される。
| ノイズなし | 聴覚ノイズ | 視覚ノイズ | 計 | |
| ○ | 150 | 50 | 50 | 250 |
| × | 150 | 50 | 50 | 250 |
| 計 | 300 | 100 | 100 | 500 |
| ノイズなし | 聴覚ノイズ | 視覚ノイズ | 計 | |
| ターゲット ○ | 150 | 50 | 50 | 250 |
| 非ターゲット × | 150 | 50 | 50 | 250 |
| 計 | 300 | 100 | 100 | 500 |
ノイズの定義
視覚ノイズが呈示されるのは、スクリーン中央にある標的エリアを中心とした8エリア ( 標的エリアの左上、上、右上、左、右、左下、下、右下 )である。視覚ノイズ課題では乱数により8エリアのいずれかが選択され、そこに標的と同時に△が呈示される。
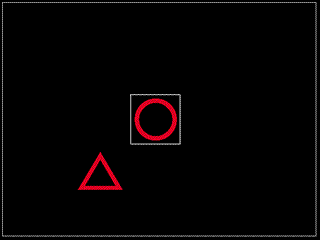
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 位置 | 左上 | 上 | 右上 | 左 | 右 | 左下 | 下 | 右下 |
聴覚ノイズは正弦波で表現される波形をもった音によって定義される。次の表に示されている8とおりの周波数から乱数により選ばれ、標的と同時に呈示される。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 音名 | A | H | C# | D | E | F# | G# | A |
| 周波数 | 440Hz | 494Hz | 554Hz | 587Hz | 660Hz | 740Hz | 831Hz | 880Hz |
タイムライン
本テストセクションは、500課題の連続によって構成される。各課題は次に示されるようなタイムラインによって定義される。 課題が始まると、ターゲットが 100ms間、ノイズが 200ms間 ( 聴覚ノイズ課題と視覚ノイズ課題の場合 )呈示される。
ターゲットが呈示されてから次のターゲットが呈示されるまでの間隔は、1300ms (1250ms + 50ms) から、2000ms (1250ms + 750ms) までが 100ms 刻みで 1/8 の確率で乱数によって選ばれる。
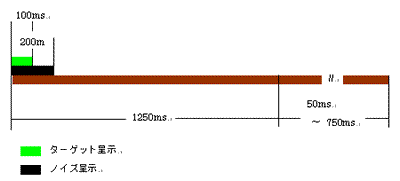
正反応、誤反応、無反応
標的刺激に対する反応についてそれぞれ正反応、誤反応、無反応を以下のように定義した。
< 正反応、誤反応、無反応の定義 >
| クリックあり | クリックなし | |
| ターゲット | 正反応(ターゲット時) | 無反応 |
| 非ターゲット | 誤反応 | 正反応(非ターゲット時) |
ターゲット呈示後 1250 msの間に被検者のクリックがあった場合のみ有効な反応時間として記録される。
予期反応
下のタイムラインの定義を参照してほしい。
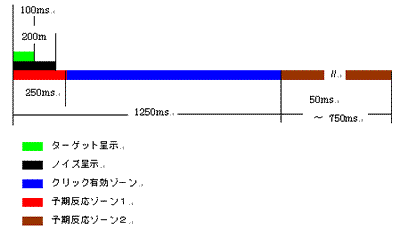
予期反応ゾーン1は、ターゲットが呈示されて 250ms 未満のゾーンである。複数の成人による実験により、250ms 以内にクリックすることは不可能であることを確認している。つまり、このゾーンでのクリックはターゲットに対する反応とは考えられないので、もし、このゾーンでクリックがあった場合、その課題は予期反応として処理される。
予期反応ゾーン2は、ターゲット呈示後 1250ms 後から次の課題が始まるまでの間に存在する。長さは乱数によって 50ms から 750msの値があたえられる。このゾーンは被検者にターゲット呈示のタイミングを簡単に予測されることを防ぐために用意されている。また、複数の児童による実験により、ターゲットに対する反応時間が 1250ms をこえることはないことを確認している。予期反応ゾーン1と同様に、このゾーンでクリックがあった場合、その課題は予期反応として処理される。
ターゲットが呈示されて 250ms 未満、または1250ms以降になされたクリックは予期反応としてカウントされる。
多発反応エラー
ターゲット、非ターゲットにかかわらず、一つの課題出題中に複数回クリックが行われた場合、多発反応エラーとしてカウントされる。
競合したエラーの優先順位
多発反応、予期反応、誤反応は互いに競合する可能性をもつ。競合した場合は以下の優先順位にしたがって判定し、カウントされる。
多発反応 > 予期反応 > 誤反応
例えば、非ターゲット呈示時に、720ms と 1370ms に二度クリックが行われた場合、多発反応・予期反応・誤反応すべての条件を満たすことになるが、優先順位にしたがって多発反応と判定される。
このように定義することにより、常に、
課題数 = 正反応数 + 無反応数 + 誤反応数 + 多発反応数 + 予期反応数
の関係が成立する
エラー数集計
被験者の検査記録ファイルに記録されたデータから、 上記の定義にしたがって以下の数値を集計する。
・ 正反応数 (Correct Response)
・ 誤反応数 (Commission Error)
・ 無反応数 (Omission Error)
・ 多発反応数 (Multiple Error)
・ 予期反応数 (Anticipatory Error)
< エラー数集計 総計 >
| ノイズなし | 聴覚ノイズ | 視覚ノイズ | 全種別計 | |
| 正反応数 (ターゲット時) |
CT(1,1) | CT(2,1) | CT(3,1) | CT(0,1) |
| 正反応数 (非ターゲット) |
CT(1,2) | CT(2,2) | CT(3,2) | CT(0,2) |
| 誤反応数 | CT(1,3) | CT(2,3) | CT(3,3) | CT(0,3) |
| 無反応数 | CT(1,4) | CT(2,4) | CT(3,4) | CT(0,4) |
| 多発反応数 | CT(1,5) | CT(2,5) | CT(3,5) | CT(0,5) |
| 予期反応数 | CT(1,6) | CT(2,6) | CT(3,6) | CT(0,6) |
計 |
CT(1,0) = 300 |
CT(2,0) = 100 |
CT(3,0) = 100 |
CT(0,0) = 500 |
また、注意の持続を調べるため、各スコアを前半部分と後半部分に分けて集計した。
< エラー数集計 前半部分 >
| ノイズなし | 聴覚ノイズ | 視覚ノイズ | 全種別計 | |
| 正反応数(ターゲット時) | CTf(1,1) | CTf(2,1) | CTf(3,1) | CTf(0,1) |
| 正反応数(非ターゲット) | CTf(1,2) | CTf(2,2) | CTf(3,2) | CTf(0,2) |
| 誤反応数 | CTf(1,3) | CTf(2,3) | CTf(3,3) | CTf(0,3) |
| 無反応数 | CTf(1,4) | CTf(2,4) | CTf(3,4) | CTf(0,4) |
| 多発反応数 | CTf(1,5) | CTf(2,5) | CTf(3,5) | CTf(0,5) |
| 予期反応数 | CTf(1,6) | CTf(2,6) | CTf(3,6) | CTf(0,6) |
計 |
CTf(1,0) = 150 |
CTf(2,0) = 50 |
CTf(3,0) = 50 |
CTf(0,0) = 250 |
< エラー数集計 後半部分 >
| ノイズなし | 聴覚ノイズ | 視覚ノイズ | 全種別計 | |
| 正反応数(ターゲット時) | CTs(1,1) | CTs(2,1) | CTs(3,1) | CTs(0,1) |
| 正反応数(非ターゲット) | CTs(1,2) | CTs(2,2) | CTs(3,2) | CTs(0,2) |
| 誤反応数 | CTs(1,3) | CTs(2,3) | CTs(3,3) | CTs(0,3) |
| 無反応数 | CTs(1,4) | CTs(2,4) | CTs(3,4) | CTs(0,4) |
| 多発反応数 | CTs(1,5) | CTs(2,5) | CTs(3,5) | CTs(0,5) |
| 予期反応数 | CTs(1,6) | CTs(2,6) | CTs(3,6) | CTs(0,6) |
計 |
CTs(1,0) = 150 |
CTs(2,0) = 50 |
CTs(3,0) = 50 |
CTs(0,0) = 250 |
前半部分と後半部分の差 CTd は以下の式で表される。
CTd(m,n) = CTf(m,n) - CTs(m,n)
< エラー数集計 差 (前半部分 ― 後半部分) >
| ノイズなし | 聴覚ノイズ | 視覚ノイズ | 全種別計 | |
| 正反応数(ターゲット時) | CTd(1,1) | CTd(2,1) | CTd(3,1) | CTd(0,1) |
| 正反応数(非ターゲット) | CTd(1,2) | CTd(2,2) | CTd(3,2) | CTd(0,2) |
| 誤反応数 | CTd(1,3) | CTd(2,3) | CTd(3,3) | CTd(0,3) |
| 無反応数 | CTd(1,4) | CTd(2,4) | CTd(3,4) | CTd(0,4) |
| 多発反応数 | CTd(1,5) | CTd(2,5) | CTd(3,5) | CTd(0,5) |
| 予期反応数 | CTd(1,6) | CTd(2,6) | CTd(3,6) | CTd(0,6) |
反応時間集計
ターゲット呈示時の正反応時のみを対象に以下の数値を計算する。
・ AT 平均反応時間 (Average of response Time)
・ SD 反応時間標準偏差 (Standard Deviation of response time)
・ CV 反応時間変動係数 (Coefficient of Variation)
ばらつきの大きさを得るために平均反応時間によって影響を受けない反応時間変動係数を求めた。反応時間変動係数は次式によって得られる。
CV = ( SD / AT ) × 100
これらの数値をノイズ種別によって集計するので、次のような表を作成することができる。
< 反応時間集計 総計 >
| ノイズなし | 聴覚ノイズ | 視覚ノイズ | 全種別計 | |
| 平均反応時間 | AT(1) | AT(2) | AT(3) | AT(0) |
| 反応時間標準偏差 | SD(1) | SD(2) | SD(3) | SD(0) |
| 反応時間変動係数 | CV(1) | CV(2) | CV(3) | CV(0) |
反応時間についてもまた、注意の持続を調べるため、前半部分と後半部分に分けて集計し、その差を求めた。
< 反応時間集計 前半部分 >
| ノイズなし | 聴覚ノイズ | 視覚ノイズ | 全種別計 | |
| 平均反応時間 | ATf(1) | ATf(2) | ATf(3) | ATf(0) |
| 反応時間標準偏差 | SDf(1) | SDf(2) | SDf(3) | SDf(0) |
| 反応時間変動係数 | CVf(1) | CVf(2) | CVf(3) | CVf(0) |
< 反応時間集計 後半部分 >
| ノイズなし | 聴覚ノイズ | 視覚ノイズ | 全種別計 | |
| 平均反応時間 | ATs(1) | ATs(2) | ATs(3) | ATs(0) |
| 反応時間標準偏差 | SDs(1) | SDs(2) | SDs(3) | SDs(0) |
| 反応時間変動係数 | CVs(1) | CVs(2) | CVs(3) | CVs(0) |
前半部分と後半部分の差 はそれぞれ以下の式で表される。
ATd(m) = ATf(m) - ATs(m)
SDd(m) = SDf(m) - SDs(m)
CVd(m) = CVf(m) - CVs(m)
< 反応時間集計 差 (前半部分 ― 後半部分) >
| ノイズなし | 聴覚ノイズ | 視覚ノイズ | 全種別計 | |
| 平均反応時間 | ATd(1) | ATd(2) | ATd(3) | ATd(0) |
| 反応時間標準偏差 | SDd(1) | SDd(2) | SDd(3) | SDd(0) |
| 反応時間変動係数 | CVd(1) | CVd(2) | CVd(3) | CVd(0) |
基本的には、これらの数値を解析の対象とする。
ダウンロード
ADHIT はダウンロードして無料で利用することができます。ただし、ソフトウェアを利用しておこる問題についてはすべて自己の責任であることをご了承ください。
軽度発達障害フォーラム
トップページ
LD 学習障害
PDD 広汎性発達障害
ADHD 注意欠陥多動性障害
発達障害に関わる情報
- 「よんでみよう」について
- チェックシート
- 二次障害・併存障害
- 事例集
- 心理検査
- ペアレントトレーニング
- トレーニング法 インリアルアプローチ
- 薬物療法
- 特別支援教育
- 視覚と学習障害について
- 生活リズム
会議室
親の会・研究機関・相談機関
その他
当サイトは学習障害,広範性発達障害,注意欠陥多動性障害等の情報を提供し、話し合う場になることを目的に
滋賀県健康福祉産業創出支援事業費助成金の助成を受け2002年に制作されました。
現在「軽度発達障害」という言葉は障害の影響が軽度であるという誤解を受けるため、単に「発達障害」に改められましたが、当サイトではこのような経緯を理解しながらも、サイトの継続性を考えてこの名称を使っていることをご了承ください。、